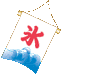使徒言行録26章1節-32節 『主よ、あなたはどなたですか』
私たちは、プロテスタント教会に属していますが、その発端となった宗教改革という運動は「原点に立ち返る」ということがその最初の目的でありました。最初にそれを行ったのは言わずと知れたマルティン・ルターでありまして、彼はカトリック教会に対して95箇条の提題と呼ばれる質問状を掲げたことから、それが問題となり、カトリック教会との決裂を余儀なくされ、プロテスタント教会の成立へと流れていくのであります。
ルターは最初からプロテストしていたわけではありません。当然最初はカトリック教徒でした。しかも聖アウグスチノ修道会の修道士として研鑽を積み、司祭となって教会に奉仕をしていた立派なカトリックでした。ルターは大変に優秀な人物であったと云われていますが、それは彼の父親が大変厳しい教育者であったからだそうです。その厳しさは並大抵のものではなく、もともと農夫から身を起こした彼の父は上昇志向が強く、子供たちにもさらに上を目指すよう常に要求し、教育をしていたと言います。その教育は時に厳格を極め、その父の姿は、ルターに「冷酷で厳格な神」というイメージを持たせる強い影響を及ぼすことになったのです。父なる神、という事は、神は父のようである。ならば神は厳格であり、厳しく、悪い事には妥協せず、時には鞭で打つような裁きを行うこともある。それがルターの神のイメージでありました。
ルターは最初からプロテストしていたわけではありません。当然最初はカトリック教徒でした。しかも聖アウグスチノ修道会の修道士として研鑽を積み、司祭となって教会に奉仕をしていた立派なカトリックでした。ルターは大変に優秀な人物であったと云われていますが、それは彼の父親が大変厳しい教育者であったからだそうです。その厳しさは並大抵のものではなく、もともと農夫から身を起こした彼の父は上昇志向が強く、子供たちにもさらに上を目指すよう常に要求し、教育をしていたと言います。その教育は時に厳格を極め、その父の姿は、ルターに「冷酷で厳格な神」というイメージを持たせる強い影響を及ぼすことになったのです。父なる神、という事は、神は父のようである。ならば神は厳格であり、厳しく、悪い事には妥協せず、時には鞭で打つような裁きを行うこともある。それがルターの神のイメージでありました。
しかしある日、聖書の学びをしているとき、突如光を受けたような新しい理解が与えられた経験をします。それは聖書を読んでいると「神の義」という言葉が目に飛び込んできたと言う事です。神の義とは厳しく裁く義であるだけでなく、神の方から与えられる恩寵の神であり、人間の悪い行いにも拘らず、神は「信仰によってのみ」救われる神であることに彼は初めて気づき、ようやく心の平安を得ることができた。これが「塔の体験」と呼ばれるルター大きな転機であったということであります。因みに塔というのは、ヴィッテンベルク大学学生寮の図書室が高い塔になっていて、そこで心が開かれる思いをしたことにより「当の体験」と後に言われるようになったわけです。とにかくここでルターが得た神学的発想は、のちに「信仰義認」と呼ばれることになり、これが宗教改革の原点になるのです。ルターは、神の恵みというものは、修道士や司祭など、ある特定の聖職者だけのものではなく、万人が「信仰義認」という神の恵みを享受することが出来ると考えます。そのため彼は聖書の翻訳をするわけです。当時の聖書はウルガタ訳と呼ばれるラテン語聖書しか使われておりませんでした。それを読めるのは聖職者だけでありました。しかしルターは誰でも聖書を読めるように、つまり母国語で神が語りかける恩恵は、誰にでも与えられる当然の権利であると考え、彼はラテン語をドイツ語に翻訳にして広く一般の信徒たちにも読めるようにしていったのであります。
とにかく、ルターという宗教改革者の原点には、神の言葉との突然の出会い、そして神からの語りかけによる「信仰義認」への気付き、そして母国語で御言葉が語られることを分かち合うことなどが、その根本にあったのであります。
皆さんの信仰の原点はどこにあるのでしょうか。信仰生活の長い方、あるいは始まったばかりの方もおられると思いますが、その中での信仰の原点を、自らの自己理解として、何をもって自分自身の信仰の原点であると言い得るでしょうか。
使徒パウロは、ダマスコ途上の回心の出来事であったと言います。今日の箇所12節以下では、そのことが克明に記されています。パウロは迫害者でした。それも筋金入りのファリサイ派であったと言われます。ナザレ人イエスに大いに反対するべきと考えるほど、そして多くのキリスト信者を牢に入れ、死刑の意思表示をし、時にはイエスを冒涜するように強制し、迫害していたと言います。それがパウロのそれまでの歩みでした。
使徒パウロは、ダマスコ途上の回心の出来事であったと言います。今日の箇所12節以下では、そのことが克明に記されています。パウロは迫害者でした。それも筋金入りのファリサイ派であったと言われます。ナザレ人イエスに大いに反対するべきと考えるほど、そして多くのキリスト信者を牢に入れ、死刑の意思表示をし、時にはイエスを冒涜するように強制し、迫害していたと言います。それがパウロのそれまでの歩みでした。
しかしダマスコ途上にて主イエスの言葉を受けるのです。使徒言行録はこのことを3度に渡って述べています。9章、22章、そして今日の26章と、事細かくその時の状況を述べています。ですからパウロにとってこれが信仰の立ち返るべき場所であった、ということなのでしょう。彼の信仰の原点がここにあるという信仰告白をこの箇所に見出すものであります。ちょうどルターにおける「塔の体験」のように、そこからその人の信仰が始まった、最も大事にしている事柄。常にそこに帰っていく場所。それがダマスコの経験なのでしょう。
回心の出来事は私たちの計画によるものではなく、神の側から来るものであります。神が与えようとして与える「ただ上からのみ来る出来事」なのです。パウロはイエス・キリストを否定し続けました。神に抗い続けたのです。そんなものは信じない。嫌だ嫌だと、キリストを排除し続けようとしたのです。神を否定し続けたのです。それに対する答えが、ダマスコで与えられたのであります。
14節にある「とげの付いた棒を蹴ると、ひどい目に遭う」という諺が意味するのは、唐突なおかしな言葉に感じられます。当時の農夫たちは牛などの家畜を動かすとき、とげの付いた鞭のような棒で打って御したわけですが、しかし中にはいう事を聞かない牛がいて、農夫に抵抗して鞭を蹴ってくることもあったと言います。しかしその牛は遂げに刺さってしまい、痛みに耐えきれず、最終的には抵抗しても無駄だ、ということを覚えていくのだそうです。そのような抗うことが出来ないという意味の諺として当時使われていた言葉がここにあるわけです。
つまり主イエスが言っているのは、パウロが一生懸命に主を否定しても主が上から与える力に対しては、それに抗うことが出来ないのだということです。否定しても、否定しても、何度も否定しても、否定しきれないものがある。それが神の業なのだと。神を否定し続けても、しかしそこには神がおられるという事実が立ちはだかるのです。
主イエスは言います「サウル、サウル、なぜ、わたしを迫害するのか」「わたしはあなたが迫害しているイエスである。起き上がれ、自分の足で立て」というのです。この語りかけが神であります。
パウロは主に言います「主よ、あなたはどなたですか」。パウロは「誰ですか」と質問しておきながら「主よ」と既に彼自身の中に答え
があるかのようであります。あなたは誰ですか。あなたの事を教えてください。あなたが私に何を与え、何を成し、何を語られるのか分かりません。何よりもまず、あなたは誰なのか分かりません。と。
パウロは主に言います「主よ、あなたはどなたですか」。パウロは「誰ですか」と質問しておきながら「主よ」と既に彼自身の中に答え
があるかのようであります。あなたは誰ですか。あなたの事を教えてください。あなたが私に何を与え、何を成し、何を語られるのか分かりません。何よりもまず、あなたは誰なのか分かりません。と。
これはモーセに対して神がご自分を啓示なさった時のことを思い浮かばせます。モーセは自分に語り掛ける声の主に言います。「あなたの仰ることは分かりました。民を導けという命令に関しても分かりました。しかしイスラエルの民を納得させるためには、それを語ったあなたが誰であるのか分からないといけません。あなたは誰なのですか」これがモーセの質問でありました。それに対する神の答えは明確です。「わたしはあるというものだ」つまりここには「存在する」という名の神が存在することを、神ご自身が開示なさったということであるのです。「私はある、私はあるという者だ。」。
この出エジプト記3章は、大変不思議な神顕現の箇所、奇跡の出来事であります。しかしここで言われている最も重要なことは、神は「ある」ということです。
神なしの世界と言われる現代社会において、この殺伐とした世の中で「生きる」とは、すなわち何を意味するのだろうか。人はそのことに悩み、苦悩し、痛みと苦しみを受けるのです。生きることの意味を見失った若者たちにとって、この世の中で生きることは何の価値があるのだろうか。仕事をリタイアして生きがいをなくし、生きる意味を失った者にとって、また、老いを迎えて、弱る心と弱る体を身に受けて、生きるとは一体何の価値があるというのか。私たちは老いも若きも、いつもこの問いを受け、その答えを探し続けるのであります。私たちの生涯のほとんどが、ここに費やされていると言っても過言ではありません。なぜ生きるのか。なぜ存在するのか。なぜ苦しむのか。なぜ生きねばならぬのか。なぜ悩まねばならないのか。そのような如何ともし難く、答えの見えない問いを受けて歩まねばならない。それが私たちの生涯の多くを占めるのであります。
神なしの世界と言われる現代社会において、この殺伐とした世の中で「生きる」とは、すなわち何を意味するのだろうか。人はそのことに悩み、苦悩し、痛みと苦しみを受けるのです。生きることの意味を見失った若者たちにとって、この世の中で生きることは何の価値があるのだろうか。仕事をリタイアして生きがいをなくし、生きる意味を失った者にとって、また、老いを迎えて、弱る心と弱る体を身に受けて、生きるとは一体何の価値があるというのか。私たちは老いも若きも、いつもこの問いを受け、その答えを探し続けるのであります。私たちの生涯のほとんどが、ここに費やされていると言っても過言ではありません。なぜ生きるのか。なぜ存在するのか。なぜ苦しむのか。なぜ生きねばならぬのか。なぜ悩まねばならないのか。そのような如何ともし難く、答えの見えない問いを受けて歩まねばならない。それが私たちの生涯の多くを占めるのであります。
しかし私たちが例え自分の生涯を見失っても、何を見つけられなくても、「神は存在する」のであります。それが私たちに与えられた答えなのであります。「あなたは誰ですか」に対 し「わたしは『ある』」と答えられる方が、私たちの神であるのです。神は「ない」のではない。「ある」のであると。
これはパウロの前に主イエスが現れたことによって、より鮮明に我々に迫ってきます。つまり彼は神の言葉をどのように聞いたのでしょうか、それは「ヘブライ語」で聞いたのであります。神の独自の言葉や、人間には解読不可能な言葉でではなく、パウロが分かる言葉で、理解可能な言葉で語られるのです。言葉は文化であります。言葉は思考であり、言葉は民族であり、言葉は意志であります。つまりその場所に神が下りてくださったということであります。「キリストは神の身分でありながら、神と等しい者であることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じ者になられました」と言われている、あのへりくだり、そして神の降下。それが私たちの分かる言葉で語られる神の本質なのであります。
マルティン・ルターは、神の言葉が分からない言語ではなく、母国語のドイツ語で語られるものであることを望み、翻訳をしました。それは神のなさろうとしたことに一致します。神は私たちに語られます。分かる言葉で。分かる仕方で。それが私たちの神なのです。
私たちはこの神の言葉に真剣に聞かねばなりません。ご自分を開示なさる、私たちに近づき、神の側から、分かる形で迫って下さる神の手を、掴みにいかねばなりません。パウロは神に捕えられました。主イエス・キリストという永遠から永遠にいまし給う神ご自身が、神の側から現れた。その恵みに気付いたのであります。私たちが如何に抗おうとも、神は神の側から、私たちのもとへと来て下さる方なのです。だからインマヌエル(神、我らと共にいまし給う)と言われるのです。神なしの世界と言われるこの現代社会において、しかし神はご自分を開示なさります。苦しむ我々に神がご自身を表されるのです。この神に従って歩みが強められたいと思います。
私たちはこの神の言葉に真剣に聞かねばなりません。ご自分を開示なさる、私たちに近づき、神の側から、分かる形で迫って下さる神の手を、掴みにいかねばなりません。パウロは神に捕えられました。主イエス・キリストという永遠から永遠にいまし給う神ご自身が、神の側から現れた。その恵みに気付いたのであります。私たちが如何に抗おうとも、神は神の側から、私たちのもとへと来て下さる方なのです。だからインマヌエル(神、我らと共にいまし給う)と言われるのです。神なしの世界と言われるこの現代社会において、しかし神はご自分を開示なさります。苦しむ我々に神がご自身を表されるのです。この神に従って歩みが強められたいと思います。
(日本キリスト教会浦和教会 2011年7月31日 主日礼拝説教)