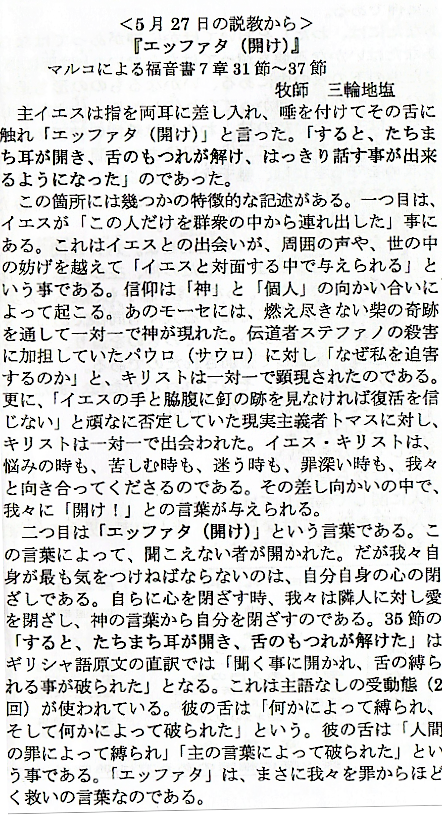<6月3日の説教から>
『四千人の給食』
マルコによる福音書8章1節~10節
牧師 三輪地塩
この箇所は決して「5000人の給食」の焼き直しなどではなく、固有のメッセージを持っている。
注目したいのは「籠」という語である。5000人の給食の話では「12の籠」がいっぱいになったとあり4000人の方では「7つの籠」となっている。どちらも「籠が溢れるほどに祝福で満たされた」事を示唆する。「籠」という単語は5000人では「コフィノス」、4000人の方では「スピリダス」。「コフィノス」はユダヤ人が旅で使う籠、「スピリダス」は異邦人が使う籠である。つまり、ここに集まっていた群衆は異邦人であることが分かる。
ところで、群衆の空腹を満たしてあげたいと思ったのは誰なのか?5000人の給食の時は、弟子たちから言い出したのであるが、4000人の給食では、主イエスが言い出していることは興味深い。ここには明らかは意図を感じる。弟子たちはここに来た4000人の群衆、つまり異邦人に対し、「神の民ではないし、神の御前に立ち得る者たちじゃないんだから、そこまで配慮する必要はない」と考えていたのではないか。なぜなら「神に選ばれたのは我々ユダヤ人であり、異邦人は神の前に立つ権利を持たないものたちだから」であると。或いは、こういう思いもあっただろう。「5000人の給食という、あの奇跡の出来事は、ユダヤ人に対して行われた。それを神の前に相応しくない異邦人相手に行うのは勿体ない」と。このような意識が、多かれ少なかれ ユダヤ人である「弟子たち」の中にあったのだろう。
だがイエスは異邦人たち(群衆)の空腹に配慮し、それを満たそうとされる。「ユダヤ人たち(弟子たち)は、彼らを神の前に立つことが出来ないというがそうではない。ユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ、困窮し、満たされない者、悲しむ者、痛む者、その全てに、神は隔てなく恵みを与えられる、とイエスは言う。7つの籠いっぱいになったパンは、まさに、全ての人、全ての種族、全ての違いの中に属する者たちへの、救いのパンとなる。